日々のつれづれと、その日のお気に入りを紹介するマイクロブログ『Day By Day』のページです。
過去の投稿アーカイブは、日本語ブログFindingsのページをご覧下さい。
Note: マイクロブログのRSSフィードURLは https://www.tatsuyaoe.com/findings/mcbg_w/feed/ に変更されました。いち早く投稿をご覧になりたい方はこちらのページへ。
最近のUK/USインディ・レーベルの音をチェックしていると、「インディ」とは思えないほど、新人でも随分豪華なミュージックビデオ(MV)を作っている。複数のAIに「販促・宣伝費はどうやって捻出するの?」と聞いたところ、「実質的にはアーティストがレーベルにローン(前借り)する形です。アーティストは“リスクは最初に負い、報酬は最後に得る存在”なのです」と返ってきた。そうした世界から離れて、音楽業を30年、レーベルを20年続けてこられたことは奇跡かもしれない。
 OE – Warning (Reconstruction Mix) (Short Edit) from “Early Techno Works 9697”
https://www.youtube.co…
OE – Warning (Reconstruction Mix) (Short Edit) from “Early Techno Works 9697”
https://www.youtube.co…
最近のUK/USインディ・レーベルの音をチェックしていると、「インディ」とは思えないほど、新人でも随分豪華なミュージックビデオ(MV)を作っている。複数のAIに「販促・宣伝費はどうやって捻出するの?」と聞いたところ、「実質的にはアーティストがレーベルにローン(前借り)する形です。アーティストは“リスクは最初に負い、報酬は最後に得る存在”なのです」と返ってきた。そうした世界から離れて、音楽業を30年、レーベルを20年続けてこられたことは奇跡かもしれない。
 OE – Warning (Reconstruction Mix) (Short Edit) from “Early Techno Works 9697”
https://www.youtube.co…
OE – Warning (Reconstruction Mix) (Short Edit) from “Early Techno Works 9697”
https://www.youtube.co…
人間は物語を自分本位に紡いでしまう性質がある。それが時に独善となり、自分を苦しめる。ヴィクトール・フランクルの説く「生きる意味」が、いつしか自分を縛る「執着(べき論)」に変貌する瞬間だ。ここでアルバート・エリスは「その解釈は認知的にゆがんでいないか? 自分を助ける考えか?」と自問し、主観の暴走を食い止めることを提唱する。フランクルとエリスは対照的に見えて、実は「解釈という刃」を使いこなすための、表裏一体の考え方だと思う。
 Dark Model – Vigilant Eyes (Short Edit) #orchestralmusic #glitch #epicmusic
https://youtube.com/shorts/sq3Qo5_d_FQ
Dark Model – Vigilant Eyes (Short Edit) #orchestralmusic #glitch #epicmusic
https://youtube.com/shorts/sq3Qo5_d_FQ
今月の Financial Timesで紹介されていた、各国の AI に対する印象を比較したグラフが印象に残っている。イプソスという調査会社のデータを図表化したものだったと思うが、日本は AI への不安も期待も、そして恩恵への実感も先進国で最下位だった。AI にユートピアもディストピアも感じない、というのは「バランス感覚がある」とするのか、「無批判・無抵抗(=お人好し)すぎる」のかは見方次第。ただ、Gemini は「ジェミナイ」と呼んでほしかったかな。
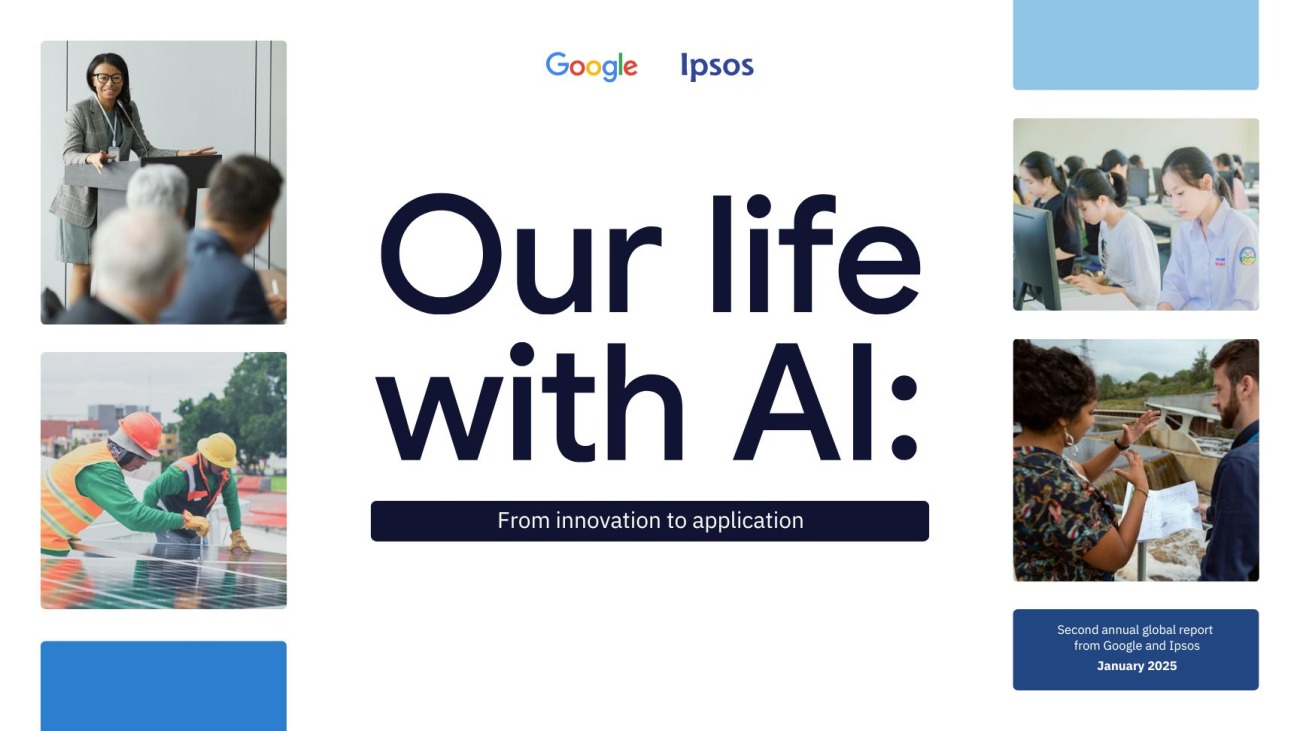 複数国にまたがるAI調査2025を実施 | イプソス
https://www.ipsos.com/ja-jp/google-ipsos-multi-country-ai-survey-2025
複数国にまたがるAI調査2025を実施 | イプソス
https://www.ipsos.com/ja-jp/google-ipsos-multi-country-ai-survey-2025
数か月前にウォーキングマシンを購入して以降、外の坂道ウォーキングの時間を半分に減らしている。そのお陰で足裏の調子は随分良いのだが、太陽の光を浴びる時間も半減してしまった。日照(メラトニン)不足対策としてLEDの室内灯を仕事中煌々と照らして使うのだが、6、7年使っているもののこれの効果はさっぱり分からない。で、いつも「常夏の島で毎日、太陽の下でランニングするのが一番」という、当たり前の結論に達する。
 Captain Funk – Running (Short Edit) #electrohouse #workoutmusic
https://youtube.com/shorts/d0qDGW_E5jU
Captain Funk – Running (Short Edit) #electrohouse #workoutmusic
https://youtube.com/shorts/d0qDGW_E5jU
最近「糸川英夫」にハマっている。そう、あの小惑星「イトカワ(ITOKAWA)」の命名の元になったロケット研究者だ。ただ、糸川氏のことをロケット研究者と呼ぶには、彼の功績は多岐に渡りすぎていて、少し気が引ける。彼の著書は中古で1円から数百円で手に入るが、書かれている内容や発想の面白さはその何百倍もの価値がある。昔よくやっていた100円のレコード箱漁りと同じく、僕はそういう拾いものの本を探すのがメチャクチャ好き。
 OE – Reincarnation (Short Edit) #breakbeat #electronicmusic #contemporarymusic
https://youtube.com/shorts/OM2wVsSo3F0
OE – Reincarnation (Short Edit) #breakbeat #electronicmusic #contemporarymusic
https://youtube.com/shorts/OM2wVsSo3F0
元Googleの思想家ジェイムズ・ウィリアムズは著書『Stand Out of Our Light』で、哲学者ディオゲネスとアレクサンダー大王の逸話を紹介する。アレクサンダーがかの有名なディオゲネスだと知り、「私にできることはあるかね?」と尋ねると、朝日を浴びていたディオゲネスは「そこ邪魔。光を遮らないで」と返した。ウィリアムズはここから教訓を引き出すが、僕は面倒な相手を動かすより自分が光の方へ動く方が手っ取り早いと思う(笑)。
 ジェイムズ・ウィリアムズ『Stand Out of Our Light』TEDxAthens
https://youtu.be/MaIO2UIvJ4g
ジェイムズ・ウィリアムズ『Stand Out of Our Light』TEDxAthens
https://youtu.be/MaIO2UIvJ4g
「私が絵を描くのは、共鳴してくれる人を求めているからではない。ただ、私の孤独を表しているだけ」と篠田桃紅さんは語った。孤独とは「埋めるもの」ではなく「結晶化するもの」。欠落ではなく充足であり、それは「自由」の別名なのだ。「自我」や「存在証明」といった強い言葉を避け、「孤独」という表現に留める。そこに、執着を脱した篠田さんならではの「粋(いき)」が宿っている。
 篠田桃紅は何をなしたのか?|美術手帖
https://bijutsutecho.com/magazine/news/report/25488
篠田桃紅は何をなしたのか?|美術手帖
https://bijutsutecho.com/magazine/news/report/25488
「言わぬが花」という言葉は好きではないけれど、我々は沈黙を大切な「知性」の一つとしてきた。でも、GoogleやAIは沈黙を検索することはできないし、機械は沈黙を知性だとは見なさない。無関心や沈黙、さらには「電源を切ること」や「回線を遮断すること」も知性の一つだと思う。こうした態度は、最近では「Attention Sovereignty(注意主権)」とも呼ぶらしい。人間が注意の主導権を奪還することができるかどうかは、つまるところ自分次第。
 OE – Hello Solitude (Ambient Visualizer)
https://youtu.be/UgXOMNP1Zhs
OE – Hello Solitude (Ambient Visualizer)
https://youtu.be/UgXOMNP1Zhs
基本的に「音の人」である僕は、世界がますます言語偏重になっていくことを残念に思っている。言語モデル(LLM)が驚くほど沢山の知的タスクをこなせるようになったからといって、「言語化こそが知能の正体」だということにはならない。そこを取り違えると、人間は言葉の奴隷になってしまう。これをどう思うかGeminiに尋ねると、「AIは人間の知性を置き換えるのではなく、人間が持つ知性の“言語化された断面”を極端に肥大化させる装置なのです」。
 マイケル・ポランニー「我々は言葉にできることよりも、ずっと多くのことを知っている」
https://www.azquotes.com/author/11748-Michael_Polanyi
マイケル・ポランニー「我々は言葉にできることよりも、ずっと多くのことを知っている」
https://www.azquotes.com/author/11748-Michael_Polanyi
各アーティスト名義ごとのYouTubeの公式チャンネルが出来たので、それぞれのチャンネル用にショート動画を制作・公開しています。広告やレコメンドなどノイズの多いYouTubeのページにわざわざアクセスして検索や試聴をするのは面倒だと感じる方も多いと思うので、ショート動画だけをまとめて抜粋紹介するページをこのウェブサイト内に作りました。気に入ったチャンネルがあれば、購読していただけると嬉しいです。
 [Video Playlist] Short Videos from YouTube OACs | Tatsuya Oe
https://l.tatsuyaoe.com/yt-shorts-oacs
[Video Playlist] Short Videos from YouTube OACs | Tatsuya Oe
https://l.tatsuyaoe.com/yt-shorts-oacs
「(広告や商業)デザインは自分を消すことだ」という意見があると聞く。僕の生業では、表現から自分を消したら終わり。ただ、万が一その手の仕事をするならば、商品やサービスを実際に使う生活者(エンドユーザー)にとってその表現が「善かどうか」で判断したい。現実的にはお金を払うクライアントがOKを出してくれれば仕事として成立するが、課題を解決し、本当にハッピーにしなければいけない相手はその先にいる。「自分問題」はそもそも課題の次元にはない。
 「アート対デザイン: 2つのクリエイティビティの違いを明確にする(英語)」
https://artincontext.org/art-vs-design/
「アート対デザイン: 2つのクリエイティビティの違いを明確にする(英語)」
https://artincontext.org/art-vs-design/
阪神・淡路大震災から31年。あの日、仕事場へ着くと皆がテレビに釘付けで、画面越しに戦慄が走った。1月17日の早朝に地震が発生してから、実家と連絡がついたのは数日後の夜だったと記憶している。両親は家具の下敷きになりかけながらも無事だった。東京にいた僕は安否を案じることしかできなかったが、震災はその後の自分の生き方を確実に変えた。
 阪神・淡路大震災31年、犠牲者へ深い祈り
https://youtu.be/OGSRQ_0fZQo
阪神・淡路大震災31年、犠牲者へ深い祈り
https://youtu.be/OGSRQ_0fZQo
AI 特集の番組で、タモリさんが 「人間性(を賛美すること)そのものが胡散臭い」と語っていた。案の定、出演者の誰もその発言の真意を確かめようとしなかった。ヴィクトール・フランクルは「過剰自己観察」という言葉で、自意識過剰がもたらす心身の疲労や機能不全を説明したが、人は「自分の前に鏡を置き、自分のことばかり考える」傾向がある。AIと人間のやり取りは、まさにこの「自己観察(言語化)の無限ループ」に陥る可能性をはらんでいる。
 過剰自己観察/反省除去 – ヴィクトール・フランクル・ロゴセラピー研究所
https://themeaningseeker.org/dereflection/
過剰自己観察/反省除去 – ヴィクトール・フランクル・ロゴセラピー研究所
https://themeaningseeker.org/dereflection/
布団にくるまり、何か映画でも見ようと思う。幸か不幸か、ジャン・リュック・ゴダールのドキュメンタリーに出会ってしまった。彼は時間芸術、とりわけ王道的な映画が持つ「物語性」を破壊することで革命と混乱を起こした。「物語を信じない」と斬り、自分の人生から作品に至るまで偶然や断片という眼差しで解体したのが、デヴィッド・ボウイだ。世界はいつしか物語まみれの時代に戻り、アルゴリズムに翻弄され、空虚な「辻褄合わせ」に躍起になっている。
 【予告編】『ジャン=リュック・ゴダール 反逆の映画作家』
https://youtu.be/jnLjmJXJims
【予告編】『ジャン=リュック・ゴダール 反逆の映画作家』
https://youtu.be/jnLjmJXJims
エドワード・サイードの代表的著書『オリエンタリズム』で、彼は西欧諸国がつくりあげた東洋へのイメージや偏見を徹底的に批判した。彼自身は複雑でパッチワーク的なアイデンティティーの持ち主であり、自らを「アウト・オブ・プレイス(場違い、部外者)」と定義している。考えようによっては(西洋に追随し帝国主義に走った)日本も「場違いな東洋」だろう。「場違いの国に生まれた場違い」として(笑)、僕は彼の主張に一筋の光を感じる。
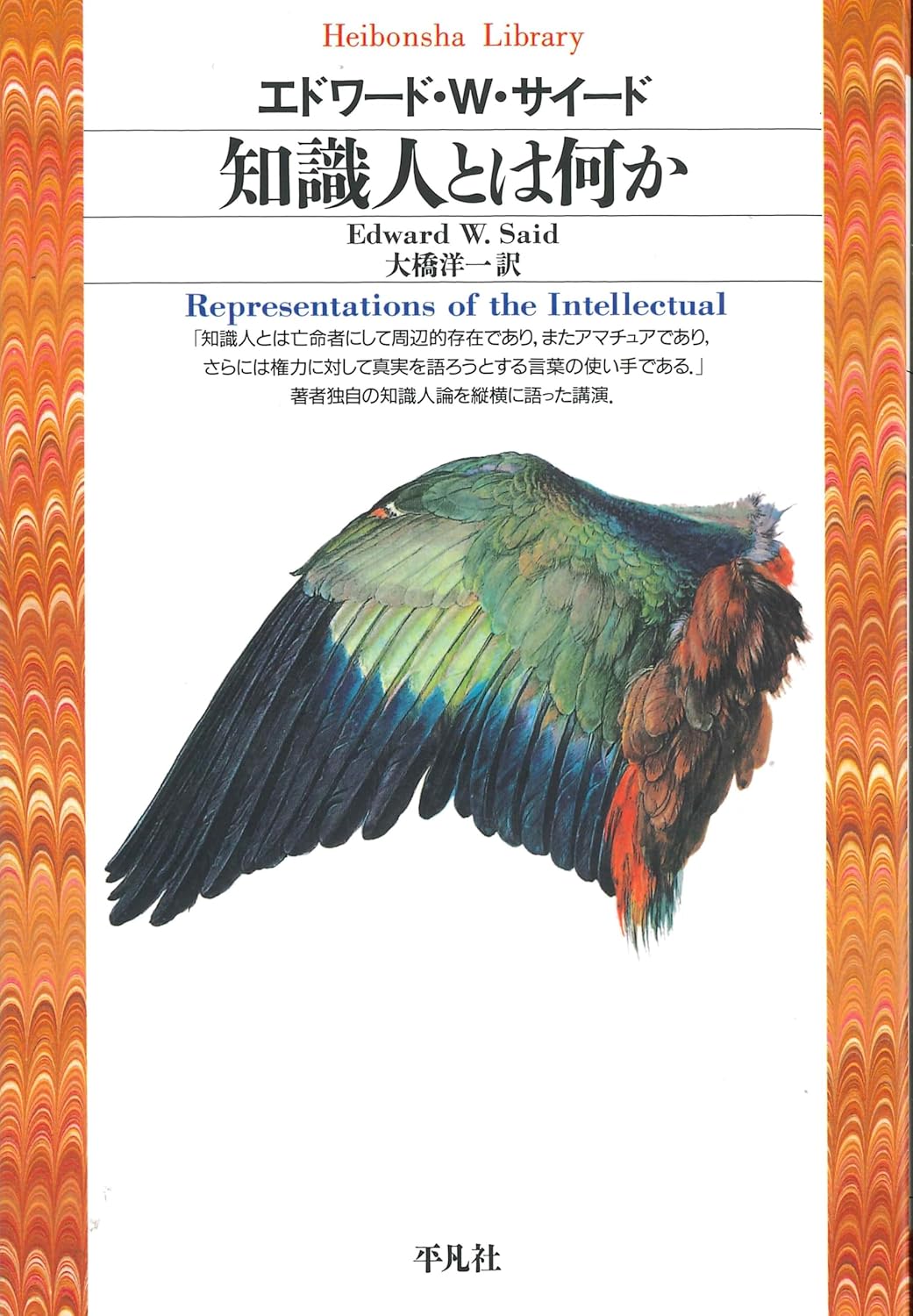 エドワード・W. サイード『知識人とは何か』
https://amzn.to/3NmlNTW
エドワード・W. サイード『知識人とは何か』
https://amzn.to/3NmlNTW
Web2.0華やかりし頃にWiredのクリス・アンダーソンが「ロングテール」という概念を打ち出した。販売機会の少ない商品でもアイテム数を幅広く取り揃えることで、総体としての売上げは大きくなるという理想郷。あれから20年経ち、Spotifyは年間1,000回再生に満たない楽曲にはロイヤリティを支払わないというルールを導入した。デジタルの世界でも管理コストはかかるし、アルゴリズムはロングテールに味方しない。現実の流通・小売と同じと言えば同じ。
 Spotify defends 1,000-stream royalties threshold after critical report
https://bit.ly/4jGvXen
Spotify defends 1,000-stream royalties threshold after critical report
https://bit.ly/4jGvXen


