Tatsuya’s daily notes with his favorites of the day.
For the older posts, please check his Japanese blog called “Findings.”
Note: The RSS feed URL of Microblog has moved to https://www.tatsuyaoe.com/findings/mcbg_w/feed/
日本では「無宗教の人が多い」とよく言われるが、正確には特定の一神教を信仰する人が少ないということだと思う。学校教育で知識や教養は得られても、人生の意味や死の捉え方、困難への向き合い方といった本質的な問題について学ぶ機会は非常に少ない。無宗教であるということは、そうした問いに対する答えを自分自身で探し、見つけ出さなくてはならないということ。それが結果として、日本社会特有の生きづらさや面倒臭さを生んでいるようにも感じる。
 Frankie Valli – Swearin To God(神に誓って)
https://youtu.be/VPVQmmzxRhU
Frankie Valli – Swearin To God(神に誓って)
https://youtu.be/VPVQmmzxRhU
日本では「無宗教の人が多い」とよく言われるが、正確には特定の一神教を信仰する人が少ないということだと思う。学校教育で知識や教養は得られても、人生の意味や死の捉え方、困難への向き合い方といった本質的な問題について学ぶ機会は非常に少ない。無宗教であるということは、そうした問いに対する答えを自分自身で探し、見つけ出さなくてはならないということ。それが結果として、日本社会特有の生きづらさや面倒臭さを生んでいるようにも感じる。
 Frankie Valli – Swearin To God(神に誓って)
https://youtu.be/VPVQmmzxRhU
Frankie Valli – Swearin To God(神に誓って)
https://youtu.be/VPVQmmzxRhU
以前、「すべてのものは他の何かに似ている」というアナロジー(類推)を使って音のデバイスを発明したウディ・ノリスについて書いたことがある。知識だけで説明するより、「〇〇は××のようなもの」と身近な例に置きかえて伝えた方が、すっと理解できるし、共感も得やすい。若い頃広告の仕事に関わっていたのも、そんな「類推の力」に惹かれたから。でも不思議なのは、難しい学問やお役所的な仕事に関わる人ほど、類推の力を使わず、わかりにくいまま伝えようとすることだ。
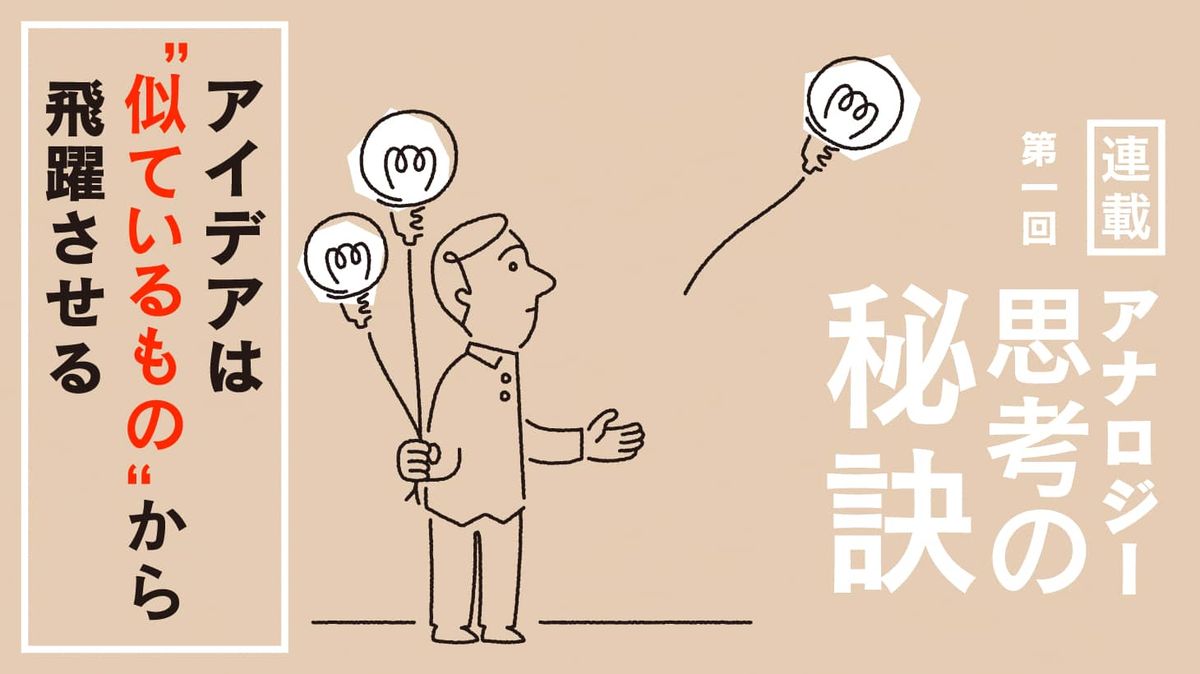 アイデアは“似ているもの”から飛躍させる:「アナロジー思考の秘訣」
https://www.cultibase.jp/articles/2007
アイデアは“似ているもの”から飛躍させる:「アナロジー思考の秘訣」
https://www.cultibase.jp/articles/2007
Pythonを使って、機械学習やディープラーニングのスクリプトを実行して遊んでいる。少し複雑だったり、大きなデータを扱ったりすると、驚くほど計算時間がかかる。その間何もせずボーッとしていると、あっという間に一日が終わってしまう。そこで、待ち時間の有効な使い方について周囲に相談してみたところ、「Pythonのアプリで問題を解いてみたら?」という提案があった。機械に学習させながら自分も学習するなんて、なんて最高にストイックなアイデア!
 AIと機械学習とディープラーニングの違いとは!?
https://youtu.be/OFMaQBV3fp4
AIと機械学習とディープラーニングの違いとは!?
https://youtu.be/OFMaQBV3fp4
数学者を描いた映画は、なぜこんなにも多いのだろう? とふと思う。自分もこれまでに結構な数の「数学映画」を観てきたけれど、フィクションの世界では「数学者=繊細で、常人には理解しがたい、ミステリアスで突飛な側面がある」という設定がデフォルトになっているように思う。ミュージシャンにも突飛さはあるかもしれないが、繊細さよりもエゴや欲望が前面に出る(笑)。だから数学映画のような”しみじみ感動話”の音楽家版は難しそうだ。
 『不思議の国の数学者』|本予告
https://youtu.be/b-LjDVcxZOo
『不思議の国の数学者』|本予告
https://youtu.be/b-LjDVcxZOo
アメリカの労働生産性が著しく低下しているという。株式や債券、投信に加え、仮想通貨市場を含めると、アメリカの金融経済は実体経済の10倍以上に膨れ上がっているとも言われる。このような異変が起きている中で、商品やサービスを通じて「価値を提供して稼ぐ」従来型の労働をばかばかしく感じる人が増えるのは、当然の帰結とも言える。Uberの運転手が「ビットコインで稼いだから、大手量販店を退社して気ままに生きることにしたよ」と話していたのが印象的。
 生産性が着実に減少する米国、労働時間も低下中| Forbes JAPAN
https://forbesjapan.com/articles/detail/80027
生産性が着実に減少する米国、労働時間も低下中| Forbes JAPAN
https://forbesjapan.com/articles/detail/80027
20年ほど前にこの世を去ったアーティスト、荒木高子氏の「聖書」プロジェクトをご存じだろうか。火災や天災により本当に焼き尽くされた聖書かと思わせる、圧倒的な荒廃の美がそこにはある。さらに、これがすべて陶(セラミック)でできているという事実にも驚かされる。彼女が「聖書(宗教書)を焼く」という行為にどういう意味を託したのか、知るすべはない。ただ、我々鑑賞者はこの作品に時代の影を映し、これからも深く考え続けることになるだろう。
 黒い聖書| 収蔵品データベース | 西宮市大谷記念美術館
https://jmapps.ne.jp/otanimuseum/det.html?data_id=588
黒い聖書| 収蔵品データベース | 西宮市大谷記念美術館
https://jmapps.ne.jp/otanimuseum/det.html?data_id=588
「残りの人生であと何回この作品を聴けるチャンスがあるだろう?」と考えるほど心に響く作品がある。それも数百枚とか数千曲(笑)。これから40年ほど元気に過ごせたとしても、聴ける音楽には限りがある。たとえ1日1曲でも、「この音楽に出会えて良かった」と感じる瞬間があれば、大抵のことは乗り越えていける。そして、もし自分の曲でそんな風に感じてくれる人が世界のどこかにいるとしたら、それはこの上ない喜び。
 John Coltrane & Johnny Hartman 1963
https://youtu.be/PUnyG01x7uk
John Coltrane & Johnny Hartman 1963
https://youtu.be/PUnyG01x7uk
ChatAIはこう答えた。「それは“トリレンマ”ですね。」トリ?何やそれ?と一瞬「鳥貴族」の黄色い看板がよぎったが、「ジレンマの三つ版」みたいなものかと解釈した。つまり、金融や政治では「三つの重要目標を同時に満たすのは難しい」という問題があるらしい。ただ日銀のやってきたことは、一部にだけ良い顔をして、日本が育んできた価値と誇りを損ねたようにも思う。こんなクオリティが高くて激安、かつ平和な鳥貴族、いや「ディスカウント遊園地」みたいな国は他にない。
 「国際金融のトリレンマ」に直面する日本、円防衛策にほころびも| ロイター
http://bit.ly/3HRc2dC
「国際金融のトリレンマ」に直面する日本、円防衛策にほころびも| ロイター
http://bit.ly/3HRc2dC
「勉強法」に関する良い本がないかと時折調べてみるのだが、自分の求める内容に出会えた試しがない。勉強法というと、大半が「効率よく、早く、ラクに」習得する方法や、試験に受かるためのコツばかり。つまり「どうゴールに辿り着くか」が主な関心事になっている。僕が知りたいのは、「そもそも何をゴールとするのか」を考えることだったり、勉強すればするほどゴールの次元が上がっていくような学びについてなんだけど、それは「勉強法」とは言わないのかも知れない。
 G. ポリア『いかにして問題をとくか』
https://amzn.to/3HQ2i3v
G. ポリア『いかにして問題をとくか』
https://amzn.to/3HQ2i3v
コム・デ・ギャルソンの2025-26年秋冬コレクションのテーマは「Smaller is Stronger」だった。今もなお反体制的な精神を創作に込める川久保さんらしいコンセプトだと感じる。2025年の現在、国同士も人同士も争いが絶えないが、いったい誰と戦うべきなのか、そもそも戦いに意味があるのか、「強さ」とは何か。そうした本質的な問いを深く考える機会や、それを促す空気自体が、著しく減っているように思う。「考えないこと」が人間を弱くする。
 “Smaller Is Stronger”: Comme des Garçons’ Revolt Against ‘Big Fashion’
http://bit.ly/4lklKE0
“Smaller Is Stronger”: Comme des Garçons’ Revolt Against ‘Big Fashion’
http://bit.ly/4lklKE0
国や企業、個人の債務を一括りにするのは無理があるとは思うが、借金が嫌いな自分は、日米の膨大な債務を「大丈夫だ」という意見には、どうしても疑問を抱かざるを得ない。この記事では、映画『マネー・ショート』のモデルの一人であるスティーブ・アイズマンの「ドルと米国債は最強」といった若干古臭いコメントを紹介している。ガザ侵攻に小躍りした彼は昨日もテレビでイランへの攻撃を「最高の儲けのチャンスだ」とぬかしていたが、世の中、ゲスの極みには際限がないね。
 米国の債務、全体像を見れば恐れるに足らず | ロイター
http://bit.ly/444ZBlR
米国の債務、全体像を見れば恐れるに足らず | ロイター
http://bit.ly/444ZBlR
僕の使っているストリーミング・サービスのアカウントには、数百のプレイリストがあって、ほぼ毎晩のエクササイズ中にその中から選んで音楽を聴いている。運動しながら新しい曲を追加することもよくある。よく聴く「MPB/Latin」というプレイリストに入っている曲のひとつが、今回紹介するこの曲。オルケストラ・アフロシンフォニカについては詳しくないけれど、バイーア(ブラジル)とアフリカのリズム&ハーモニーが融合したこの大所帯サウンドを、好きにならないはずがない。
 Orquestra Afrosinfônica – Orín
https://youtu.be/8IvIcWujIbk
Orquestra Afrosinfônica – Orín
https://youtu.be/8IvIcWujIbk
数年前「シーフードや野菜をスパイスで和えて、ビニール手袋をつけて手づかみで食べる米南部のケイジャン料理は、食材とスパイスさえ揃えば意外と簡単に作れる」と書いたことがある。ただし、実際にはその食材やスパイスを揃えるのが手間で、日本ではそもそもロブスターを扱うスーパー自体が少ないのも現実。そんな中、東京と大阪に本場の味に近いケイジャン料理を楽しめる店があると知った。「手づかみシーフード」で検索してみてください。
 Epic Seafood Feast at THE BOILING CRAB
https://youtu.be/OtRWA7oPEbo
Epic Seafood Feast at THE BOILING CRAB
https://youtu.be/OtRWA7oPEbo
かつてパット・メセニーがケニーGを痛烈に批判した「事件」があったらしい。エンタメ系のゴシップに興味がない僕は、その話も最近まで全然知らなかったし、知っても「へぇ、そうなんだ」くらいの感想しかない。ただ、才能や実力に関係なく、表現者が他の表現者を一方的に「裁く」のは感心しない。結局は、相手のオーディエンスを見下しているか、その人の境遇に嫉妬しているだけのように見えてしまうからだ。とことん“Mind your business(自分のことを心配しろ)” で行きたい。
 ケニー・Gとジャズ・ポリスの攻防| サライ.jp
https://serai.jp/hobby/1076889
ケニー・Gとジャズ・ポリスの攻防| サライ.jp
https://serai.jp/hobby/1076889
音楽で生きている自分がこう言うのは変かもしれないが、もし感情のスイッチである扁桃体や自律神経がなければ、もっと気楽に生きられるのでは…と突拍子もないことを考えることがある。だから、感情を交えずに発想や仕事を助けてくれるAIには感謝しているし、政治家なんて全部AIでいいんじゃないかと思うことすらある。かつて日本では「感情を持つAI・ロボット」が話題になったけど、そんな技術が普及したら逆にますます面倒で生きづらい国になるだろう。
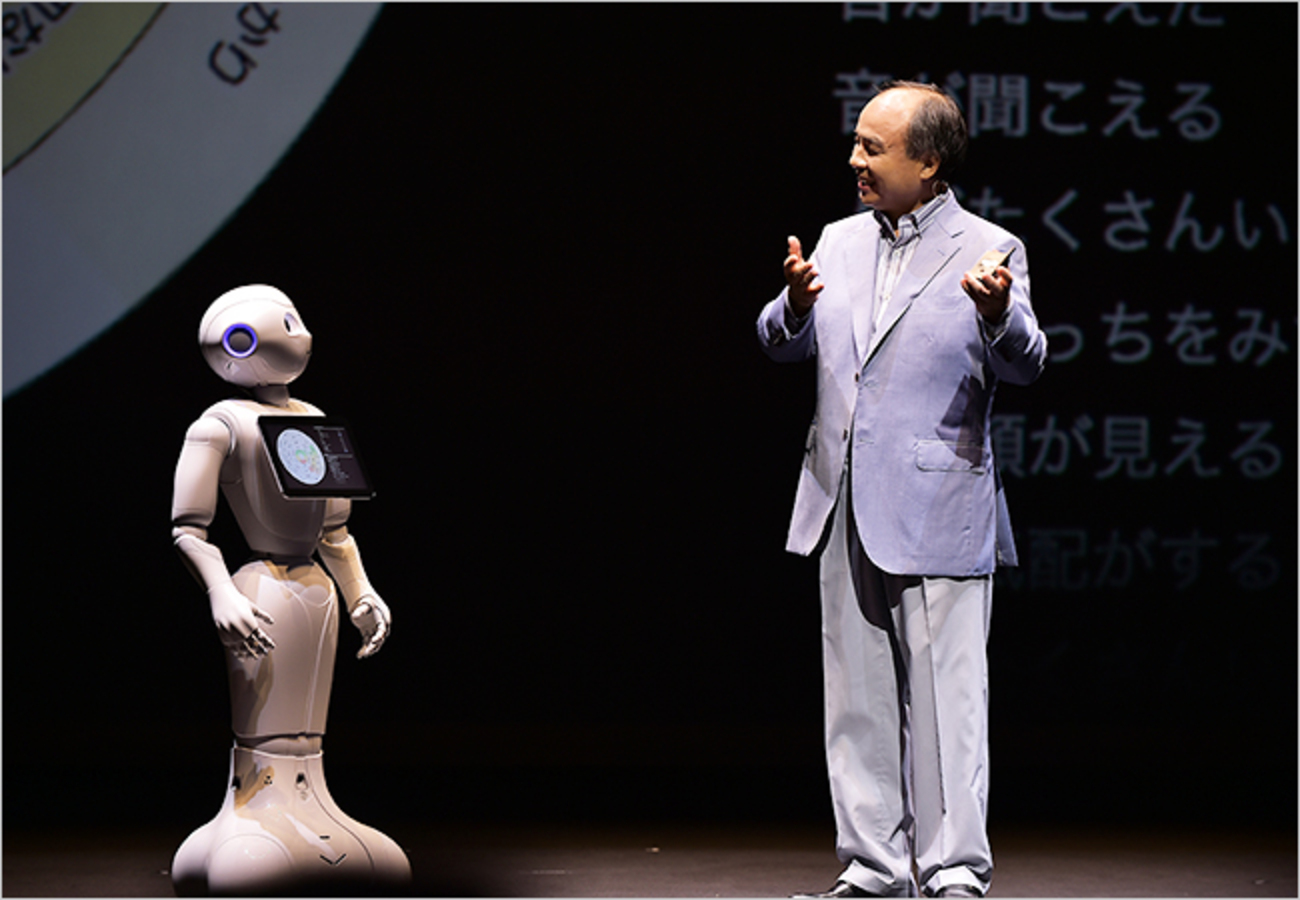 感情を持つロボット「Pepper」の一般発売を開始 – ソフトバンクニュース
https://www.softbank.jp/sbnews/entry/20150707_01
感情を持つロボット「Pepper」の一般発売を開始 – ソフトバンクニュース
https://www.softbank.jp/sbnews/entry/20150707_01
近所にトルコ人が多く住む地域があって、そこのスーパーの品ぞろえがユニークだった。ピスタチオ入りの緑の焼き菓子「バクラヴァ」や、すごく伸びるアイス「ドンドゥルマ」など、大手チェーンでは見ない食べ物を売っていて発見の連続。あの不思議な食感のアイスがたまに恋しくなるのだが、最近はなんと、家庭でそれに似た食感のヨーグルトを楽しめる。どうやら「クレモリス菌」が鍵らしい。
 This Turkish Ice Cream Doesn’t Melt – YouTube
https://youtu.be/4p9EI6cRB0c
This Turkish Ice Cream Doesn’t Melt – YouTube
https://youtu.be/4p9EI6cRB0c


