ニーズ変わればバージョンも変わる
楽曲の様々なバージョンを作ることは、それぞれのニーズに応えるという実務面だけでなく、クリエイティブな側面でもメリットがあると言えます。バージョン違いや曲の断片という、いわば「仕掛品」から思わぬ新しいアイデアが生まれることがあるからです。
楽曲の様々なバージョンを作ることは、それぞれのニーズに応えるという実務面だけでなく、クリエイティブな側面でもメリットがあると言えます。バージョン違いや曲の断片という、いわば「仕掛品」から思わぬ新しいアイデアが生まれることがあるからです。
音楽ライセンスという仕事は、日本国内と海外でその取り扱い方がかなり異なります。今日はその辺りの事情のさわりと、音楽ライセンスの領域でインディペンデント・レーベル、アーティストがどう成果を出せるかという可能性について。
ブルガリアの友人が手掛けているブランドDemobaza、桑沢デザイン研究所で開催されている「ワダエミ衣装空間」、そしてワダエミさんが衣装を手掛けた黒澤明監督「乱」の、武満徹氏によるサウンドトラックを紹介。
スティーヴン・ソンドハイムの作品をはじめとして、ミュージカル音楽には、ポピュラーミュージックとしても非常に聴き応えのある、「プログレッシブ(進歩的)・ポップ」と呼んでも差し支えない位の、良質でポップな楽曲が沢山あります。今日はバート・バカラックが全面的に音楽を手掛けた映画「Lost Horizon」の一部を紹介。
Tatsuya Oe Updated: 2024/11/6 水曜日
最近のUK/USインディ・レーベルの音をチェックしていると、「インディ」とは思えないほど、新人でも随分豪華なミュージックビデオ(MV)を作っている。複数のAIに「販促・宣伝費はどうやって捻出するの?」と聞いたところ、「実質的にはアーティストがレーベルにローン(前借り)する形です。アーティストは“リスクは最初に負い、報酬は最後に得る存在”なのです」と返ってきた。そうした世界から離れて、音楽業を30年、レーベルを20年続けてこられたことは奇跡かもしれない。
 OE – Warning (Reconstruction Mix) (Short Edit) from “Early Techno Works 9697”
https://www.youtube.co…
OE – Warning (Reconstruction Mix) (Short Edit) from “Early Techno Works 9697”
https://www.youtube.co…
人間は物語を自分本位に紡いでしまう性質がある。それが時に独善となり、自分を苦しめる。ヴィクトール・フランクルの説く「生きる意味」が、いつしか自分を縛る「執着(べき論)」に変貌する瞬間だ。ここでアルバート・エリスは「その解釈は認知的にゆがんでいないか? 自分を助ける考えか?」と自問し、主観の暴走を食い止めることを提唱する。フランクルとエリスは対照的に見えて、実は「解釈という刃」を使いこなすための、表裏一体の考え方だと思う。
 Dark Model – Vigilant Eyes (Short Edit) #orchestralmusic #glitch #epicmusic
https://youtube.com/shorts/sq3Qo5_d_FQ
Dark Model – Vigilant Eyes (Short Edit) #orchestralmusic #glitch #epicmusic
https://youtube.com/shorts/sq3Qo5_d_FQ
今月の Financial Timesで紹介されていた、各国の AI に対する印象を比較したグラフが印象に残っている。イプソスという調査会社のデータを図表化したものだったと思うが、日本は AI への不安も期待も、そして恩恵への実感も先進国で最下位だった。AI にユートピアもディストピアも感じない、というのは「バランス感覚がある」とするのか、「無批判・無抵抗(=お人好し)すぎる」のかは見方次第。ただ、Gemini は「ジェミナイ」と呼んでほしかったかな。
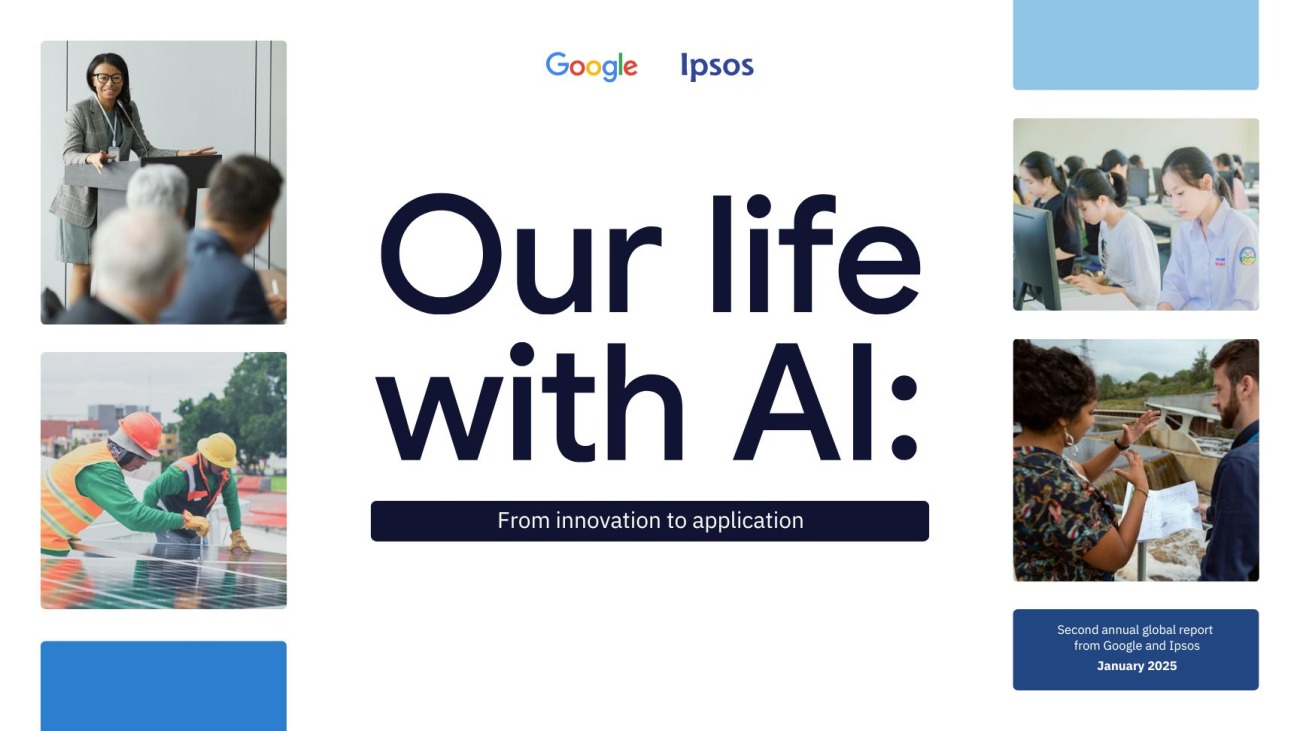 複数国にまたがるAI調査2025を実施 | イプソス
https://www.ipsos.com/ja-jp/google-ipsos-multi-country-ai-survey-2025
複数国にまたがるAI調査2025を実施 | イプソス
https://www.ipsos.com/ja-jp/google-ipsos-multi-country-ai-survey-2025
