マイクロブログ・アーカイブズ 2024年6月
ニュースのコメント欄やSNSなどでは、世間の出来事を全部自分事として捉える風潮があるけれど、自分と直接関係のないことに逐一反応していると、本当に大事な判断を正確に行うための落ち着きとエネルギーを使い果たしてしまう。過度の「内面化(internalization)」をやめて、必要以上に当事者意識を持たないように努めることはストレスフリーへの第一歩。
ニュースのコメント欄やSNSなどでは、世間の出来事を全部自分事として捉える風潮があるけれど、自分と直接関係のないことに逐一反応していると、本当に大事な判断を正確に行うための落ち着きとエネルギーを使い果たしてしまう。過度の「内面化(internalization)」をやめて、必要以上に当事者意識を持たないように努めることはストレスフリーへの第一歩。
英国の詩人ワーズワースの有名な詩の一節に、”The Child is father of the Man”という、逆説的な表現が出てくる。子供は大人の父親(原型)、つまり子供の時に抱いた感動や心躍る気持ちがその後の自分を形作る、という意味だと思う。彼にとっては虹から受けた感動がそれにあたる一方で、僕にとっては海だったり音楽だったりする。
超多作な作家で知られたアイザック・アシモフは、「なぜ時間を過去に設定した本を書かないのか?」と聞かれて、「過去を書くには下調べが必要になる。自分で捏造できる未来と自分が既に知っている現在に絞って書いた方が生産的だよ。」と答えたとか。アウトプットで飯を食う自分にとっては示唆に富む話だけど、彼の場合「既に知っている事」が膨大だった。
クリエイターにはコンセプト型の人とストーリー型の人がいると思う。もちろんどちらも創作にとって必要な資質なのだが、その「重心の置き方」は表現形態や作品、アーティストによって随分異なる。本来は時間芸術である音楽の中にも、ストーリーよりもコンセプトに大きく寄りかかったタイプの作品もある。ただコンセプトは手品やとんち(あるいは屁理屈)と同じく、鮮度と説得力を保つのが大変。
成功に再現性は必要だろうか?幸運は、努力や行動で引き寄せられる要素と、本当に「たまたま」で「再現性ゼロ」な要素が入り混じっている。曲がヒットするのも、宝くじが当たるのも、大統領に選ばれるのも、実はあまり変わりがないように思う。差が出るのは、その後の「手に入れた幸運の使い方、転がし方」。普段の積み重ねや精神力がモノを言うのはその時。
よく練られたシステム(仕組みとルール)とテクノロジーは人為的ミスを減らし、生産性を上げ、結果として社会と経済を潤す。一人一人の注意力やスキルの向上、そして残業(!)、つまり「人間の努力負担」で解決できると考える風潮を絶たないと、「人が頑張れば頑張るほど、誰も幸せにならない」社会から抜け出せなくなる。
人間はいつか死ぬ存在だからこそ、何かをやってみようと思い、自分の人生を出来るだけ意味のあるものしようと取り組む。ナチスの強制収容所で体験した極限状態において彼を支えたものは「生きる意味」だと、ヴィクトール・フランクルは説く。僕は古典的な精神医学や心理学からは距離を置いているけど、実体験に根差した彼の考察は説得力がある。
人は誰でも自分の中に「アーティスト」と「裁判官(ジャッジ)」を抱えているという。二役とも、一日の仕事量の上限はほぼ決まっている。自分と関係のない事柄に首を突っ込んだり、むやみに事を複雑にして判断の数を増やすと、人が本来持っているアーティスト資源=創造性や発想力、飛躍力が劇的にしぼんでいく。
紙の束を渡されて、「制限時間内に出来るだけ沢山の紙を、教室の向こう側に飛ばしなさい」と言われたら?紙飛行機を一つ一つ作って飛ばそうとする人は、紙をくしゃくしゃに丸めた玉を放り投げる人に惨敗する。後者の解決法に眉をひそめる大人もいるだろうが、現実世界で瀕死の状況を切り抜けたり社会に変革を起こすのは後者のやり方。答えは一つでないことを教わる機会はあまりに少ない。
Tatsuya Oe Updated: 2024/11/5 火曜日






今朝、英語圏のSNSでは「エヌビディアは実際に利益を出している。どこが一体AIバブルなんだ?」という暴論が飛び交っていた。実のところ、株価よりも売上が膨張している状況こそバブルとして深刻だ。「売れているから大丈夫」という主張は、裏を返せば「売れなくなった瞬間に、それを支える理屈が何一つなくなる」という危うさと表裏一体だから。日本をダンスフロアにしてどんちゃん騒ぎをしている海外の機関投資家に要注意。音楽が止まった時、彼らはいない。
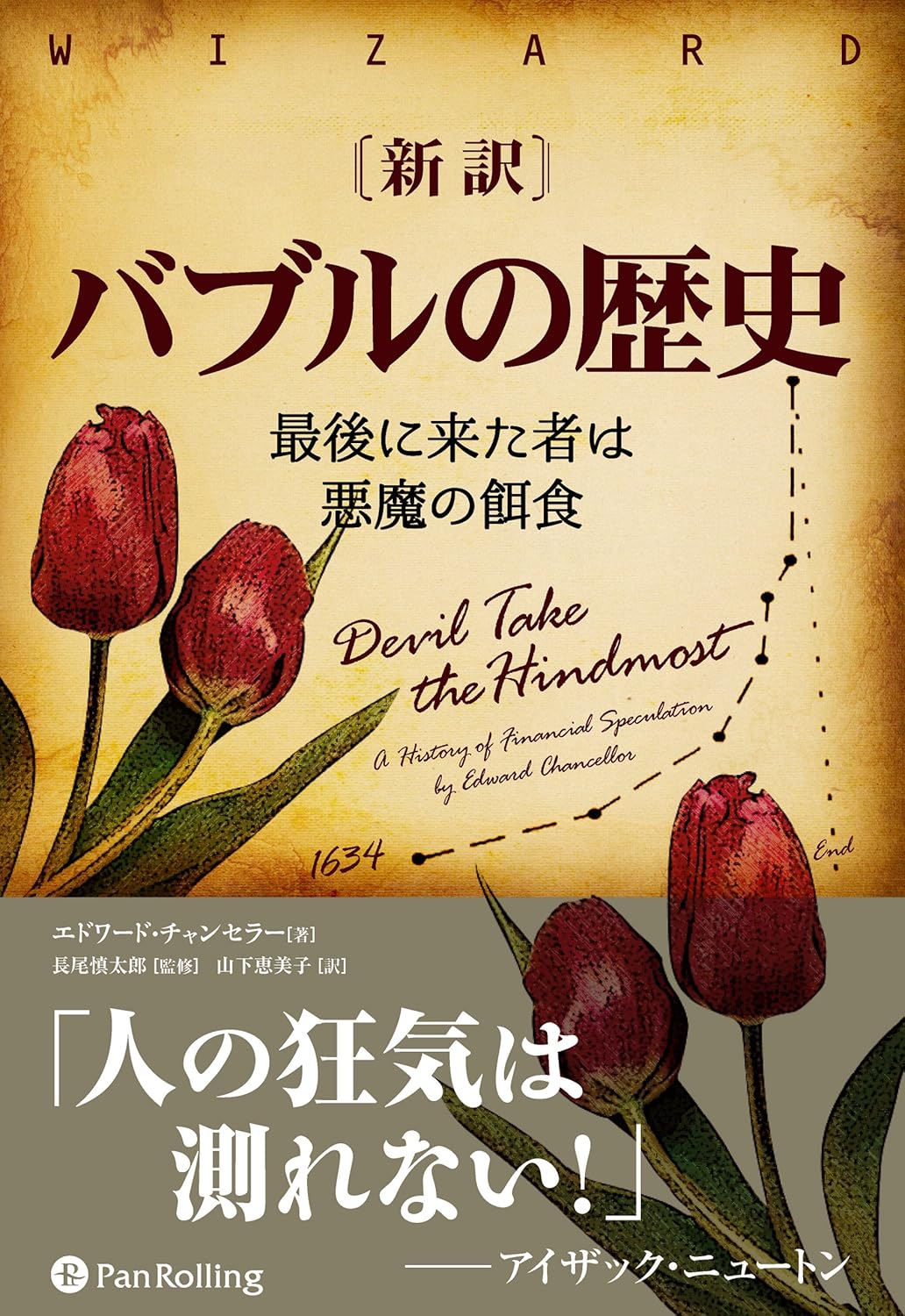 エドワード・チャンセラー 『新訳 バブルの歴史』
https://amzn.to/4rBaq9L
エドワード・チャンセラー 『新訳 バブルの歴史』
https://amzn.to/4rBaq9L
子どもの頃から数年に一度は引っ越しをしてきた。国内外あわせて、少なくとも15か所前後は住んだことがある。どの街にも相性の良し悪しがあり、当然ながら自分にとって完璧な場所はない。ただ、環境を変えれば必ず何か気付きを得られるから、悩むヒマがあれば行動してしまったほうが早い。若い頃は故郷がないことを寂しく思ったこともあるが、移動と再訪を繰り返すうちに、故郷とは結局、自分の記憶の中にしか存在しないのだと割り切れるようになった。
 Soul II Soul, Caron Wheeler – Keep On Movin'
https://youtu.be/1iQl46-zIcM
Soul II Soul, Caron Wheeler – Keep On Movin'
https://youtu.be/1iQl46-zIcM
白地に黒の四角が2個あった時、その間が徐々に狭くなって一つに見えてしまう仕掛けがあるとする。どこまで差が小さくなったら一つに融合して見えるかを測った時、2.1kHz(少し高めの音)を聞きながらその仕掛けを見た被験者は、その差の見極めが鋭くなったという。音で視力がよりクリアになったりぼやけたりするというのは、とても興味深い。私たちの五感は独立しているのではなく、脳の中で複雑に響き合い、一つの世界を作り上げている。
 Captain Funk – Girlfriend #disco #funk #housemusic #uplifting
https://www.youtube.com/shorts/zdsgFdOcIKg
Captain Funk – Girlfriend #disco #funk #housemusic #uplifting
https://www.youtube.com/shorts/zdsgFdOcIKg
