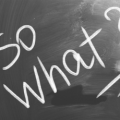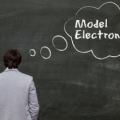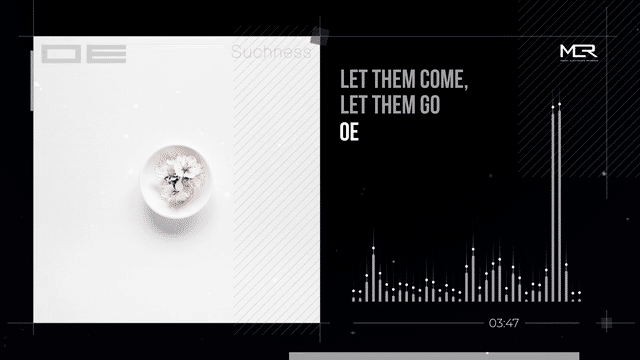日本の英語学習において、「アクセント」の話はあまり話題に上りませんが、イギリス、オーストラリア、アメリカなど、各国で英語をネイティブに話す人達ですら、別の地域のアクセントが入った英語を聞き取ることが難しい場合があると聞きます。英語となると、「話すこと」がとかく重要視されますが、このアクセントの問題を含めて、相手の話を「聞くこと」にもっと意識的になっても良いのではないでしょうか。
ニューヨーカーも字幕でセリフを追う?ブリティッシュ・アクセント
このところイギリス英語にハマっています。ハマっているといっても、熱中しているわけではなくて、沼地にはまっている方のハマり方です(笑)。僕の知り合いで英語をネイティブに話す人は、北米はさておきヨーロッパの人でも割とアメリカナイズされた英語を話す人が多いので、ブリティッシュ・アクセントに馴染む機会がそれほど多くありません。
(注:ここでいう「アクセント」は、必ずしもイコール「なまり」ではありません。自分が一番標準的な英語を話していると思っている各国のネイティブ・スピーカーにとっては、アクセントという呼び方すら抵抗があるようです。)
普段よく見るBBCのキャスターが話す英語は割とクセが少なく、まだついて行けるのですが、所謂コックニー訛りの強い人やケルト系の方の英語はかなり難しい。ただ、これは北米の人達にとっても同じらしく、ネイティブ同志でも聞き返さないと分からないことがしばしばあるとのことです。ニューヨークに住むアメリカ人の(かなり高い教育を受けた)英語教師の友人が、中世のイギリスが舞台の人気テレビ番組を見る時に、字幕でセリフを追わないと理解できないと言っていたのが印象的でした。「ネイティブスピーカーならどの国のアクセントが入った英語もすんなり理解できるはずだ」という認識は、私たち非ネイティブ・スピーカーが勝手に抱いている「神話」なんです。
聞き返すことで、相手とのコミュニケーションの「地ならし」をする
日本語の会話ならば、(訛りが強いもしくは滑舌の問題で)相手の言う事が聞き取れない場合は、躊躇なく「今何て言ったの?」と聞き返すことが出来るのに、英語だと例え同様のケースであっても、まず自分の語学耳(力)に非があると思って、聞き返すのも躊躇してしまう。そんな経験を皆さんもお持ちだと思いますが、やはり躊躇しないで出来る限り聞き返すクセをつけた方が良いと思います。講演などの一方的なスピーチやグループでの会話の場合は諦めるしかないですが、一対一の会話の場合はお互いのキャッチボールあってこそですから、こちらの理解度を誠実に相手に伝えること、会話のペースや語彙のレベルを揃えてもらう(つまり、「地ならし」をする)ように働きかけるそのやり取りの円滑さこそが、内容以上に重要なこともありますからね。もちろん、せっかちな人はその作業を放棄して(=会話を停止して)しまうこともあるでしょうが、その場合はウマが合わないのだと開き直るのも、時には大事かと思います(笑)。
とはいえ、毎回開き直っていては会話から得られるチャンス、楽しさを自ら捨ててしまうことになるし、前述の様にグループでの会話やスピーチの様な「一対多」のシチュエーションの場合は、自分だけ会話から取り残されてしまいますから、それは出来る限り避けなくてはいけません。ツアーなどに限らず、僕は時々「自分以外全員ネイティブ」な状況に出くわすことがあるのですが、それがオーストラリアン・ネイティブやブリティッシュ・ネイティブ(一概には言えませんが、歴史的経緯もあり両者のアクセントは割と近いと言われています)の場合だと、まず会話について行くことにエネルギーを相当量使ってしまいます。
聞けば、開ける
どんな言語であれ、コミュニケーションは「話すこと」より、まず「聞くこと」からはじめるべきだと思いますし、最近日本ではGlobish(グロービッシュ)が話題になっているとはいえ、ネイティブ・スピーカー達はグロービッシュの存在などまず知らないし、このレベルの英語に足並みを揃えてコミュニケーションを取ってくれるはずもないですから、「様々なネイティブ英語を正確に聞く」という課題を克服する必要性は永遠に存在するものなのでしょう。英語でのコミュニケーションにおいて、よく「日本人は発言をしない」というコメントを聞きますが、発言が少なくても、相手の内容が聞き取れてさえいれば、しっかり把握してさえいれば、コミュニケーションの主導権を握ること、自分の存在感を出すことは可能です。その逆はないということは、日本人同士の議論や会話でも、饒舌な人が必ずしも説得力があり、主導権を握るわけではないのと同じです。英語の話になると、「話すこと」に対して極端に意識が向いたり、重要視されるという風潮には、ちょっと違和感があるんですね。
そんなわけで、ここ最近は訛りの強い英語が聞けるシチュエーションを探しては、聞き取りできるか試してみたりしている次第です。自己紹介を21のアクセントでこなす、この”21 Accents” のビデオは皆さんも既にご存知かも知れませんね。この手の「英語アクセントネタ」はYoutubeでも沢山見つけられますが、興味深いのは、ジャパニーズ英語のアクセントを正確に真似出来る西洋人(もしくはそれを試みている人)はまずいないことです。それだけ英語と日本語は共通点の少ない、「遠い言語」だということかも知れません。