創造のレッドオーシャン&ブルーオーシャン
アメリカでは、日本以上にクリエイティブな表現の画一化が進んでいます。結果に結びつかない個性やクリエイティビティは要らない、そんな行き過ぎた金銭的成果主義が犠牲にするものは想像以上に大きい。この風潮に屈して自分の創造性に限界を作ったり、蓋をしないように環境を設計していく努力が問われる時代にさしかかっているように思います。
アメリカでは、日本以上にクリエイティブな表現の画一化が進んでいます。結果に結びつかない個性やクリエイティビティは要らない、そんな行き過ぎた金銭的成果主義が犠牲にするものは想像以上に大きい。この風潮に屈して自分の創造性に限界を作ったり、蓋をしないように環境を設計していく努力が問われる時代にさしかかっているように思います。
米ハフィントン・ポストによる Dark Model 「Saga」アルバムレビューと、収録曲「Avalon」のバックストーリーを紹介します。ハフポストのレビューでは、5点中4.5点の高評価を頂いて、とても嬉しく思っています。
Dark Model「Saga」についてのニュース/音楽メディアでのレビュー紹介第四弾です。今回はカナダのメディアに掲載された記事をほぼ完全翻訳で紹介します。『Saga』は映画三部作分(トリロジー)に匹敵する、自己設定のための音楽であるという、鋭い視点で書かれたレビューをお楽しみ下さい。
動画サイトの登場によって、企業から個人まで映像を制作・公開する機会が増え続けている一方で、映像に音楽を同期させて使用する権利=「シンクロ権」について参考になる情報はまだまだ少ないと言えます。今回はこのシンクロ権を中心に、日本とアメリカでの音楽著作権の管理方法・オペレーションの仕方の違いを解説します。
人間を「理性的な動物」と呼ぶことがありますが、生きていくために理性よりもずっと優先して理解されるべき、人間が本来持つ「動物性」について、渡米2年を経た今考えてみます。栗本慎一郎からドナルド・トランプまで、人間の動物性を垣間見る参考図書も紹介。
アメリカで現在ブームとなっている「リップ・シンク(口パク)」を紹介します。職人芸的な上手さではなく、いかにエンターテインメントとしてインパクトがあるかを競う「エア芸」が特徴です。ここから垣間見える、二次創作の「オープン化」の未来、その最もゲリラ的な手法としての「エア化」についても考えてみます。
2015年、年始のご挨拶。昨年はDark Modelのアルバムを制作・リリースし、各方面から嬉しい反響を頂けたことが最も大きな収穫でした。皆さんにとって2015年が素晴らしい年となるといいですね。今年もよろしくお願いします。
アナログレコード復活を通り越し、カセットテープや8トラックがクールだというローテック礼賛が沸き起こる一方で、新しい集客&集金装置としてのEDMシーンが活況を呈しています。接点がなさそうでいてどちらも「脱・CDビジネス」が根っこにあるとも言える、この二つのトレンドについて考察してみます。
「Dark Modelはシネマティックなスコアと最新形のダブ的な音響美学を融合させるという野心的な試みに挑む稀有な存在であり、アルバムを聴けばその試みが全面的に成功していることが分かる。」 Skopemag.com「Dark Model」アルバムレビュー
Tatsuya Oe Updated: 2024/11/6 水曜日






今朝、英語圏のSNSでは「エヌビディアは実際に利益を出している。どこが一体AIバブルなんだ?」という暴論が飛び交っていた。実のところ、株価よりも売上が膨張している状況こそバブルとして深刻だ。「売れているから大丈夫」という主張は、裏を返せば「売れなくなった瞬間に、それを支える理屈が何一つなくなる」という危うさと表裏一体だから。日本をダンスフロアにしてどんちゃん騒ぎをしている海外の機関投資家に要注意。音楽が止まった時、彼らはいない。
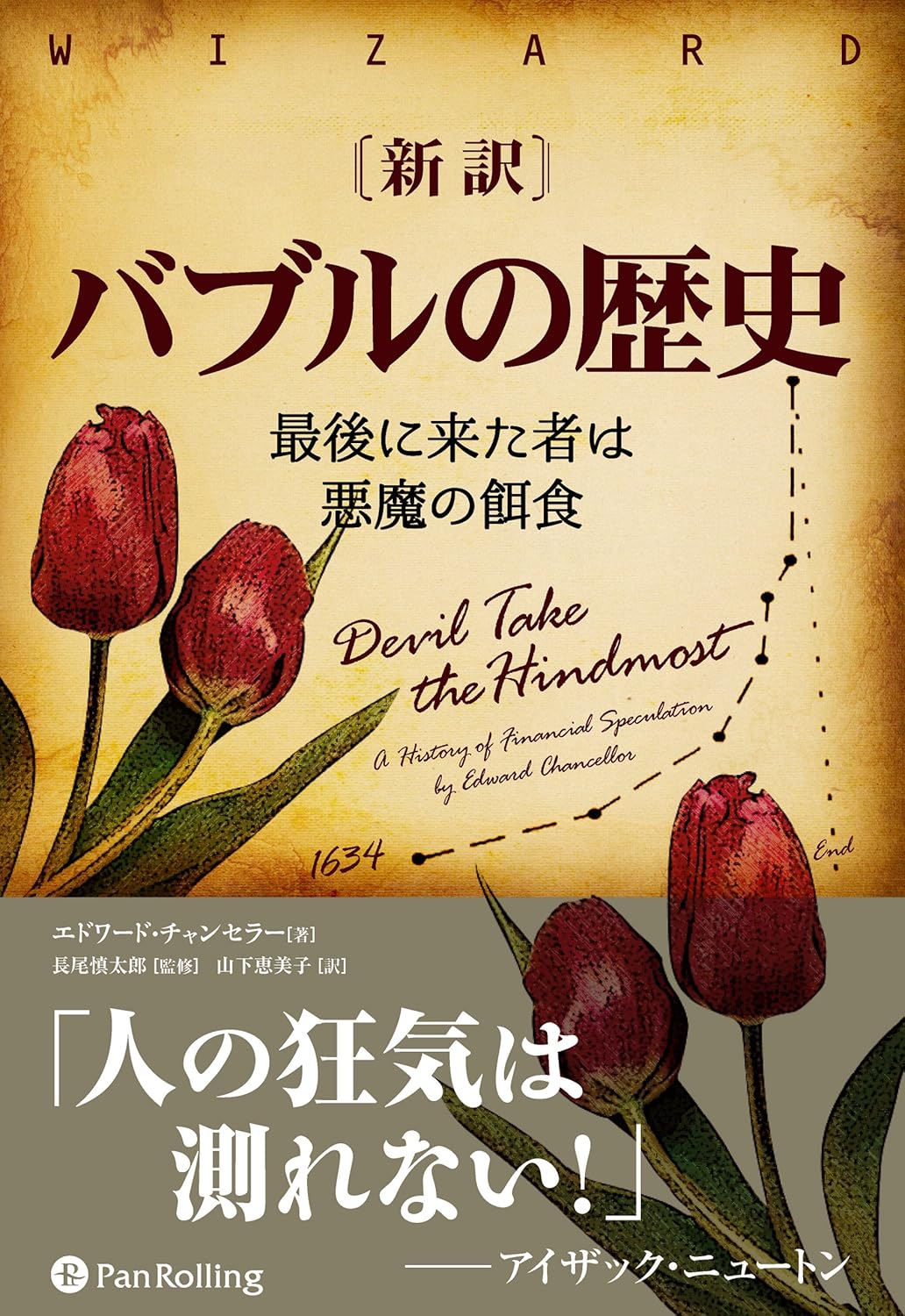 エドワード・チャンセラー 『新訳 バブルの歴史』
https://amzn.to/4rBaq9L
エドワード・チャンセラー 『新訳 バブルの歴史』
https://amzn.to/4rBaq9L
子どもの頃から数年に一度は引っ越しをしてきた。国内外あわせて、少なくとも15か所前後は住んだことがある。どの街にも相性の良し悪しがあり、当然ながら自分にとって完璧な場所はない。ただ、環境を変えれば必ず何か気付きを得られるから、悩むヒマがあれば行動してしまったほうが早い。若い頃は故郷がないことを寂しく思ったこともあるが、移動と再訪を繰り返すうちに、故郷とは結局、自分の記憶の中にしか存在しないのだと割り切れるようになった。
 Soul II Soul, Caron Wheeler – Keep On Movin'
https://youtu.be/1iQl46-zIcM
Soul II Soul, Caron Wheeler – Keep On Movin'
https://youtu.be/1iQl46-zIcM
白地に黒の四角が2個あった時、その間が徐々に狭くなって一つに見えてしまう仕掛けがあるとする。どこまで差が小さくなったら一つに融合して見えるかを測った時、2.1kHz(少し高めの音)を聞きながらその仕掛けを見た被験者は、その差の見極めが鋭くなったという。音で視力がよりクリアになったりぼやけたりするというのは、とても興味深い。私たちの五感は独立しているのではなく、脳の中で複雑に響き合い、一つの世界を作り上げている。
 Captain Funk – Girlfriend #disco #funk #housemusic #uplifting
https://www.youtube.com/shorts/zdsgFdOcIKg
Captain Funk – Girlfriend #disco #funk #housemusic #uplifting
https://www.youtube.com/shorts/zdsgFdOcIKg
