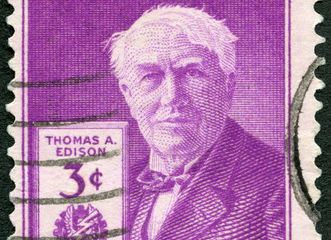我々クリエイターは、作品を創ることに集中しすぎて、「自分の仕事を持ってして、社会にどういう影響・結果をもたらしたいのか」という仕組み・力学を考えることをおろそかにしがちです。そこを考えないと、時代や「スタイル」に翻弄されて時間を浪費してしまう可能性がある。自分と、自分の生んだものに社会的な影響力を持たせることにかけて、発明以上に執着心を持って活動をしたエジソンの話も交えて、創作と社会の力学の関係について考察します。
「スタイル」と政治はニワトリと卵?
週末は新曲作りをしていました。実は作りかけている曲で7割止まりのものが沢山あり、しばらくはそれらのコンプリートに追われそうです。そういえば、アメリカの友人がMaroon5(マルーン5)の新曲「Moves Like Jagger」についてメールをしてきて、「タツヤはああいう感じの曲得意だから一緒に作らないか?ああいうスタイルはこちらで今人気だよ。」と提案をしてきてくれたのですが、「”ああいうスタイル”自体が人気」なのか「Maroon5が”ああいうスタイル”をやるから人気」なのかといえば、後者の方が確実に要因として大きいでしょう。それならLMFAOのはっちゃけたスタイルに注目した方がまだ破壊力が…、ってそういう話ではないんです(笑)。
確かに最近はアメリカでもダンスミュージック的なスタイルを強く打ち出した曲がチャートを席巻することも多いですが、チャートやヒットというのは曲やアーティストのポテンシャルもさることながら、様々な関係者の努力やポリティカルな要素が上手く働いた結果ですから、その力学や因果関係を踏まえずして、ヒットした曲と同じスタイルの曲を作ればイケるというわけでは全然ないわけですよね。その手法が功を奏するのは強者が「最後にかっさらう戦略(Winner Takes All)」として行った場合のみです(上のMaroon5の例しかり、American Idol で露出がピーク時に達したタイミングでリリースしたJennifer Lopez @ランバダ、しかり)。
政治という「人・社会・時代の力学」について考える、学ぶ
それよりも、自分が本来持っている換え難い特性を持ってして周囲の人達にどう働きかけ、巻き込むのか、もしくは持ちうる手段・資産でそういったパワー・ポリティクスの世界にどうコミット出来るのか(もしくはどう距離を置くのか)を考える方が現実的でしょう。オバマさんの演説を真似ても大統領になれる訳ではないし、そのオバマさんすら賞味期限が過ぎようとしている(かも)、なんて本物のポリティクスの世界に話を近づけるのは無理やりすぎますが(笑)。ただ、どんな世界であれ、ビジネスであれ、また会社であれ、政治を避けては通れない以上、政治の力学について考える・学ぶこともまたある程度は必要かと思います。
昔読んだトム・ピーターズの「ブランド人になれ」という本に、「権力は必要善」というくだりがありました。権力というとヒトラー、スターリン、毛沢東、ジョージ・ブッシュ(笑)の様な人物や、マキアヴェリ的な権謀術数、帝王学を連想させてしまいがちですが、ガンジーやキング牧師、ダライ・ラマ、ネルソン・マンデラの様な権力の使い方もあると。例が両極すぎましたね(笑)。間を取ってジョブスも入れましょうか。
「人の心を動かす」という事には様々なレベル、規模、局面がありますが、いずれにしても「何を持ってして誰にどう働きかけるのか、どういう印象を持ってもらうのか、どういう影響・結果をもたらしたいのか」という仕組み・力学を考えないで済む仕事・職業というものは存在しません。音楽はそのコンテンツだけでも個人の心を揺さぶるパワーを持ちえます(もしくは持ちえるとされている)が、ビジネスもしくは社会/文化の一要素としての音楽はそれだけでは全然終わらず、コンテナー(リスナーからレコード会社、流通、プロモーター、イベンターなどそれを運ぶ・伝える・再生産する人全て)、さらにはそれを後押しする社会的なレバレッジ(影響力、政治力、サポートする集団など)や時代的なモメンタム(勢い)があってこそ成り立っているものですから、様々な角度でこの「必要善」についても考え、向き合っていく必要があると思うのです。
これは音楽に全く限らないことで、現在僕らがガンジーやキング牧師の演説を聞いただけでは(当時その場にいた人達ほどは)激しく心を揺さぶられることがない様に、コンテンツやスタイル、その商品特性の話だけを切り取ってその影響力を測るのは、その間にある背景や(その時固有に持ちえた)勢い、力学などを端折りすぎとも言えますし、コンテンツ・商品やスタイルを美化しすぎ、二次元視しすぎのようにも思えます。むしろ大事なのは、見えずらいけれどもある程度普遍化できる、そこに働く「人・社会・時代の力学」の方であり、そこを抜かしてしまうと、「iPadばりに突き抜けた商品を作ればブレイクする」とか、「ビートルズ並に良い楽曲を作れば世界がアッと言う」とか、この大量消費&高度情報社会が飽和しきった時代にそぐわぬ、モノ作り偏愛・商品力/コンテンツ偏重な発想に暴走してしまう危険があります(日本のビジネス番組やドキュメンタリーによく見られる傾向です)。この点はモノ作りを美化し、思い入れを持ちやすい僕らクリエイターこそ気をつけなければならないでしょうね。
トーマス・エジソンのアグレッシブさ
皮肉ながらも、それを僕らに教えてくれるのはこの大量消費社会のきっかけを作った張本人の一人でもある「発明王」かつ「実業家」のエジソンなのかも知れません。先日ジェームス・ダイソン氏のインタビューを紹介した際に、エジソンの発明・モノ作りへの執着心、不屈の努力ぶりについて書きましたが、それと同時に彼はそれを「伝える」、さらに言えば「自分と、自分の生んだものに社会的な影響力を持たせる」ことにかけて、発明以上に鬼気迫る執着心を持ってアグレッシブに活動をしたということはよく知られています。(「快人エジソン – 奇才は21世紀に甦る」など参照のこと)
追記:関連ページ